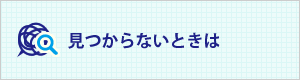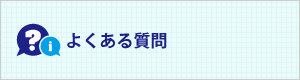須々万大名行列
須々万地区伝統芸能の継承
八朔祭(はっさくまつり)
周南市須々万の里には古くから伝わる八朔祭があります。この祭りは五穀豊穣・悪疫鎮散の祈願をこめて行なわれていて、夜祭りとして近隣からも多くの人が訪れています。この祭りの起こりは元和5年(1619)須々万の里に疫病が大流行し、村人達はこの疫病平癒のため飛龍八幡宮において昼夜を通して疫病鎮静の大祈祷を行なったところ、程なくして病が収まったので、それに感謝するために始まったといわれています。また、この祭りの始まりが八月朔日であったことから『八朔祭』と呼ぶようになったといわれています。
そして長い年月の間にこの例祭日も幾度か変わり、今では毎年8月25日に最も近い土曜日に行われています。

八朔祭
須々万大名行列
延喜元年(901)の正月、菅原道真が57歳のとき大宰権師として左遷され九州へ下向される途中、時の周防の国司でもあった土師信貞(はじのぶさだ)が菅原道真と同族であったので国司の館にお立ち寄りの際、国庁の大行司・小行司役の庁吏が送迎をなした事を古式にのっとって儀式化したものが始まりです。明治の初め頃から大行司の行列(47名)、小行司の行列(47名)に大名行列の形式が組み込まれ一段と古式豊かなものとなり、現在の「須々万大名行列」の原型となりました。現在では大行司・小行司を併せた一つの行列となっていますが、女性の薙刀が加わるなどより一層華やかなものとなっています。
また他の言い伝えによれば、大行司の着衣は「竿衣」といって浄衣に竿の付いた衣を身に付けています。これは菅原道真が国司の館をお発ちになるとき小行司に遅れをとられた大行司が慌てて、物干し竿に干してあった衣を竿が付いたまま身に着けて見送られたことによるものと言われています。

昭和32年8月25日(片地)

国庁の大行司
須々万大名行列保存会
須々万地区では、コミュニティ団体である『まちづくり推進協議会』のもとで、郷土の伝統文化の振興を目的に「須々万大名行列保存会」を平成2年1月13日に発足しました。
主な活動として、毎年の八朔祭に参加するとともに伝統演技についての研究や衣装・用具などの整備などを行っています。また平成16年の「萩開府400年記念萩時代祭り」をはじめ、平成18年には「国民文化祭やまぐち」、平成20年には「周南市郷土芸能大会」というように、八朔祭以外の色々な行事やイベントにも参加しています。
また保存・継承活動として、須々万大名行列保存会と須々万公民館は須々万中学校への大名行列の演技指導や沼城小学校への「伝統芸能継承教室」などを積極的に行っています。これからも、須々万地区の伝統文化であるこの大名行列を守り継ぎ、後世に保存していくために活動していきます。