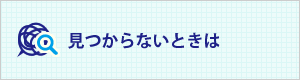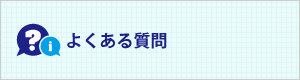富田方面の文化財
30.大神板碑

板状の自然石の板碑で、上部に地蔵菩薩の梵字が刻まれた県下でも古い板碑です。刻まれた文字から、「念阿」を供養するために、応安3年(1370)に建立されたことが分かります。
所在地:富田2096(大神)
地図<外部リンク>
31.木造薬師如来立像

鎌倉時代のものとみられる一木造りで、地方作としては優秀な像です。藤原期の様式に習いながらも鎌倉風がみられます。がっしりした量感があり、丁寧に彫られています。
所在地:河内町1番※河内薬師堂
地図<外部リンク>
32.木造阿弥陀如来立像

藤原時代末期のものとみられる一木造りで素朴な地方作の像です。彫りの浅い流麗な衣文や、ふくよかな面相をしています。宝永2年(1705)とある修理銘も、史料として重要です。
所在地:富田2960(新町中)※浄真寺
地図<外部リンク>
33.浄真寺(じょうしんじ)板碑

鎌倉時代中期に建てられた、胎蔵界曼荼羅の中台八葉院の梵字を刻む県内唯一の板碑です。当地方の信仰の様子を知る貴重な資料です。
所在地:富田2960(新町中)※浄真寺
地図<外部リンク>
34.浄真寺五輪塔

岩塊を彫りだした五輪塔です。古風な成型から鎌倉時代中期のものと思われます。県内にこのように古い時代の一石から彫りだした五輪塔は珍しく貴重なものです。
所在地:富田2960(新町中)※浄真寺
地図<外部リンク>
35.木造聖観世音(しょうかんぜおん)菩薩立像

鎌倉時代に作られた寄木造りの像です。もと浄宝寺の本尊として作られ、周防三十三観音霊場の第17番札所として崇敬されてきました。亥の年ごとに開帳され、この地方の信仰と深く結びついています。
所在地:土井1丁目5-1※建咲院
地図<外部リンク>
36.建咲院板碑

自然石で量感のある堂々たる板碑です。正安2年(1300)の銘があり、県下で6番目に古いものです。梵字は墨書されていたと思われます。鎌倉時代の民間信仰の様子を知るうえで貴重な資料です。
所在地:土井1丁目5-1※建咲院
地図<外部リンク>
37.建咲院文書(もんじょ)

永禄2年(1559)から近世初期にかけて、毛利氏が建咲院に宛てた文書などです。陶氏菩提寺であった建咲院へ毛利氏の対応を示すもので、毛利氏の宗教政策の一端を示す史料として重要です。
所在地:土井1丁目5-1※建咲院
地図<外部リンク>
38.銅造鰐口(わにぐち)

慶長13年(1608)に金光寺鰐口として鋳造されたものです。製作技法的には中世・近世双方の技法が用いられ、鋳傷や亀裂などもなく、保存も良好です。
所在地:富田2438(新町東)※荘宮寺
地図<外部リンク>
39.連歌懐紙(れんがかいし

宝暦9年(1759)から明治5年にかけて興行された連歌の懐紙と、興行のために寄進された硯箱と関係文書です。懐紙は一部を欠きますが、用具とともに伝えられ、近世の文芸資料として貴重なものです。
所在地:宮の前1丁目6-13※山崎八幡宮
地図<外部リンク>
40.山崎八幡宮本山(ほんやま)神事山車

元禄15年(1702)に始まったという本山神事の際に用いられる山車です。山車の組み立てには、釘ではなくカズラなどを使い、車輪も松の輪切りを使うなど、古い様式が良く残されています。
所在地:宮の前1丁目6-13※山崎八幡宮
地図<外部リンク>
41.勝栄寺板碑

延徳3年(1491)に建てられた板碑で、阿弥陀如来の梵字が彫られています。蓮座などの彫り方に硬さがあり、室町中期以降の特色をみせています。阿弥陀如来種子で、かつ紀年銘がある板碑として貴重です。
所在地:中央町3-10※勝栄寺
地図<外部リンク>