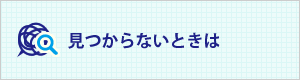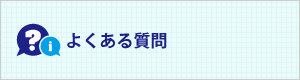湯野・福川方面の文化財
20.湯野板碑

応永12年(1405)に建てられた板碑です。3基は一組と考えられ、左塔と右塔はその断面から一つの石を割って製作したことが分かります。地元では「石仏さん」として親しまれています。
所在地:湯野(佐古)
地図<外部リンク>
21.貝籠(かいごもり)五輪塔群

弘安4年(1281)と刻まれた塔を含む、組み合わせた五輪塔10基です。鎌倉末期から室町時代にかけての造立と思われます。これらは本来の目的である本尊供養から、次第に墓塔化していく過程を示す実例といえます。
所在地:夜市(貝籠)
地図<外部リンク>
22.紙本(しほん)着色八幡縁起絵巻

室町時代に製作されたと思われる、市内に残る唯一の八幡縁起です。上巻は神功皇后が新羅へ赴く様子が、下巻は帰国後、応神天皇を出産する様子が描かれています。土佐派の様式で、写実的で丁寧に描かれています。
所在地:夜市556(宮の下)※鷹飛原八幡宮
地図<外部リンク>
23.鷹飛原八幡宮の神像

鎌倉時代に造られた神像です。女神像2躯は神功皇后と三女神、男神像4躯は武内宿祢、仲哀・応神・仁徳天皇にあてられます。鎌倉時代の特色をよく表している像で、八幡縁起絵巻と併せ、中世神社の貴重な資料です。
所在地:夜市556(宮の下)※鷹飛原八幡宮
地図<外部リンク>
24.羽島一号古墳

古墳時代後期(6世紀)に築かれた横穴式石室の古墳です。後世、羽島八十八箇所の札所として信仰されていて、天井石や副葬品はすでに失われています。
所在地:羽島2丁目3
地図<外部リンク>
25.福川本陣跡

山陽道福川宿において、参勤交代の大名などの休憩・宿泊の場所でした。代々福田家が預かり、表口17間、奥行き14間で門構えのある屋敷でした。天保9年(1838)に建てられた門が名残を留めています。
所在地:本陣町
地図<外部リンク>
26.八代集(はちだいしゅう)秀逸
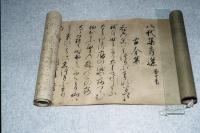
8つの勅撰和歌集から10首ずつ秀歌を選び、和歌の手本として書かれたものです。伝来する由来ははっきりしませんが、永正3年(1506)に飛鳥井雅康が、甲斐の武田信達に授けたものです。
所在地:西桝町
27.真福寺板碑

乾元2年(1303)に建てられた板碑です。地蔵菩薩と不動明王を一体として祀るもので注目に値します。鎌倉時代の当地方の庶民信仰のありさまを示すものとして重要です。
所在地:福川中市町6-27※真福寺
地図<外部リンク>
28.永源山横穴墓出土遺物

古墳時代後期(6世紀)の横穴墓から出土した遺物で、須恵器や土師器、鉄刀、ガラス玉などのほか、土器に入れられたままハマグリやカラス貝などの供物が残っていたことが、古墳の祭祀を知るうえで貴重な資料です。
所在地:福川中市町1-7 ※新南陽民俗資料室
地図<外部リンク>
29.日地板碑

文明2年(1470)に建てられた三角錐形の堂々とした自然石の塔婆で、地蔵菩薩の梵字が彫られています。室町中期の信仰とともに、庶民が塔婆を建てることができた民度の高さを示すものです。
所在地:富田2丁目14-1
地図<外部リンク>