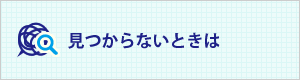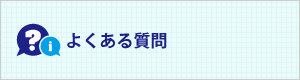建咲院什物(けんしょういんじゅうもつ)

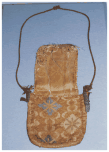
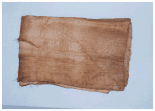
県指定文化財(工芸品)
指定年月日:平成16年12月10日
所在地:周南市土井一丁目建咲院
地図<外部リンク>
時代:室町時代後半
建咲院は、1482年に陶興房(すえおきふさ)が、父・弘護(ひろもり)と母の菩提を弔うため創建した寺です。
建咲院什物はこの寺に伝わる道具類で、毛利元就(もうりもとなり)から建咲院の隆室知丘(りゅうしつちきゅう)に寄進されたものと伝えられています。
いずれも中国製の織物で保存状態も良く、県内はもとより全国的にも室町時代後半の染織品の仏具として珍しいものです。
九条袈裟(くじょうけさ)
縦は最大134.5cm、横は下辺369cmの袈裟で、牡丹(ぼたん)や唐草(からくさ)などの模様の金襴(きんらん)が用いられています。金襴は中国の明で製作されたもので、この時期の基準的な作例として貴重なものです。
血脈袋(けちみゃくぶくろ)
仏教の教えを受け伝えてきたという系図を入れる袋です。表地は赤茶地の大内菱と唐草模様の朱珍(しゅちん)が使われています。朱珍は絹織物の一種で、中国では明の時代に盛んに織られました。
坐具(ざぐ)
僧が儀式等で座るときに敷く敷物です。麻布を銀襴(ぎんらん)で縁取ってあります。
付(つけたり)
念珠(ねんじゅ)
水晶と菩提樹(ぼだいじゅ)の実を交えた念珠です。
香合(こうごう)
抹香を入れる木製の円形容器です。
瓢形水晶(ひさごがたすいしょう)
瓢形をした水晶で切り口が欠けたようになっています。