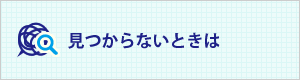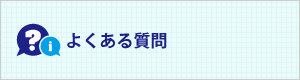花笠踊

県指定無形民俗文化財
指定年月日:昭和51年3月16日
所在地:周南市大字八代
地図<外部リンク>
「花笠踊」(はながさおどり)は、鶴の里八代の魚切部落に400年以上前から伝わる踊りで、昭和43年(1968年)には、山口県無形文化財に指定され、昭和45年(1970年)の大阪万博や昭和60年(1985年)のつくば科学万博で日本の民俗芸能を代表するものの一つとして上演され、全国に知られることとなりました。
この踊りは、いい伝えによると、陶晴賢の謀反により最後を遂げた大内義隆の追善供養のために庶民が捧げたのが始まりだといわれています。
また、一説には、かくれている大内義隆を誘い出そうとして陶晴賢が村人に踊らせたものともいわれています。
花笠踊は、当初、7年に一度 8月朔日(8月1日)に奉納されていましたが、明治以降は8月26日の二所神社の八朔風鎮祭で踊るようになりました。祭りの当日、夕方魚切の中心山の神社に勢揃いして、先頭の道分けに続いて大花灯篭をおし立て、大締太鼓、はやし方、音頭取りのあとに花笠をかぶった踊り子が続き、里人の持つちょうちんに守られて踊り隊が二所神社に参詣して行きます。

演者は、道分け8名、調子2名、調庄2名、男踊子12名、女踊子12名、音頭とり数名、大花灯籠1名、高張提灯数名から構成されます。
古来、踊子は未婚の男女に限られ、特に調子と調庄とは未婚の長男にかぎるとされています。また、花灯篭や娘踊子のつける花笠が大きくたいへん美しいものとして見物客の目をひくものです。
踊りは、道分けの乱れと称する棒踊りに続き、「花の踊り」「六調子踊り」「四季の踊り」「宿所踊り」「巡礼踊り」「五色踊り」「姉御踊り」「牛若踊り」「千代松踊り」の9つが踊られます。
昭和46年に国の『記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択されたもの』に選ばれ、昭和51年、県の無形民俗文化財に指定されました。