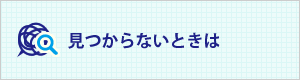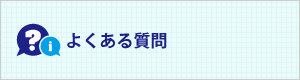諫鼓踊(かんこおどり)
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新

県指定無形民俗文化財
指定年月日:昭和51年3月16日
所在地:周南市大字呼坂
地図<外部リンク>

諫鼓踊は、勝間地区に伝わる民俗芸能で、7年ごとの秋季例祭において、熊毛神社で奉納されます。
伝承によると、豊臣秀吉が朝鮮出兵の途中、「勝間」という地名が吉瑞として熊毛神社に戦勝を祈願し、凱旋の際には、お礼に太刀や神馬とともに「諫鼓踊」を奉納したと言われています。
また、陶晴賢が大内義隆を滅ぼしたときの様子を模したとも言われています。
踊りは、手木(拍子木)1人、旗持ち1人、ほら貝ふき1人、棒使い1人、大聖1人、小聖1人、音頭鶏(胴取り)2人、踊り子12人、僧1人で構成されています。
この踊りは、中世の田楽に起源をもつものと考えられており、歌を伴わず、太鼓と鉦を主楽器として用い、団扇と棒を用具として加える点に特色があり、華麗な服装と花冠、腰輪などが踊りをいっそう引き立たせています。
「勝間諫鼓踊保存会」の方々により保存・伝承されており、次回の式年祭は令和6年(2024)10月を予定しています。