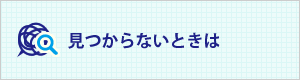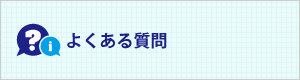勝栄寺土塁及び旧境内(しょうえいじどるいおよびきゅうけいだい)
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新

県指定文化財(史跡)
指定年月日:昭和62年3月27日
所在地: 周南市中央町(ちゅうおうちょう)
地図<外部リンク>
時代:室町時代
勝栄寺は、陶弘政を開基とする時宗寺院(現在は浄土宗)です。創建されたのは、陶氏が富田保へ移住して間もない時期(1350〜80年)と考えられています。
この時代の時宗は、布教と併せて北朝方の動静をさぐり、南朝方の連絡をすることにあったとみられており、富田保が大内惣領家の橋頭堡的位置を占めていたことからして、勝栄寺の政治的・軍事的性格は強まらざるを得ませんでした。
勝栄寺は、江戸時代の「防長寺社由来」絵図に土塁と濠が描かれており、土塁の北・西部は今日まで残存し、濠も近年まで蓮田としてその面影をとどめていました。
南北朝動乱期の陶氏が置かれた厳しい立場からみて、この時期に防御施設として、土塁や環濠が設けられたのではないかと考えられています。
繁栄した中世の富田保や富田津の歴史だけでなく、めまぐるしい動きをみせた中世防長史の舞台として、現存する数少ない貴重な史跡です。