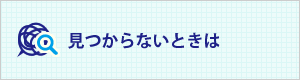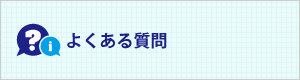金梨子地菊桐紋散雲蒔絵鞍・鐙
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
金梨子地菊桐紋散雲蒔絵鞍・鐙(きんなしじきくきりもんちらしくもまきえくら・あぶみ)


県指定文化財(工芸品)
指定年月日:平成2年3月30日
所在地:周南市毛利町
毛利就挙(周南市美術博物館寄託)
地図<外部リンク>
[原則非公開(特別展時のみ公開)]
時代: 安土桃山時代
乗馬は古墳時代には日本に伝わっており、当時の古墳から馬具付きの馬型埴輪や馬具類が多く出土しています。その後、主要な交通手段として、最近まで生活の中で重要な役割を果たしてきました。
徳山毛利家に伝来するこの鞍と鐙は、表面に梨の実の皮に似せて金粉を散らした上に、菊と桐、棚引雲(たなびきぐも)を配した金梨子地菊桐紋散雲蒔絵という漆塗りの技法で装飾されています。
付属の天明4(1874)年の覚書によると、毛利元就(もとなり)の孫、輝元(てるもと)が豊臣秀吉より拝領し、さらにその子・徳山藩祖就隆(なりたか)に伝えたものであるといいます。
毛利氏は、天正10(1582)年の備中(びっちゅう)(現、岡山県)高松城の戦いで、当時織田信長の家臣であった羽柴秀吉と和睦し、秀吉の全国統一後は五大老の一人となるなど、強いつながりをもっていました。装飾的な見事さとともに、徳山毛利家の歴史の一端を知る史料でもあります。