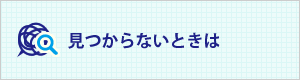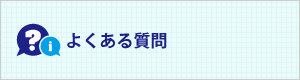金造菩薩形坐像(きんぞうぼさつぎょうざぞう)
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新

県指定文化財(彫刻)
指定年月日:昭和62年3月27日
所在地:周南市湯野(ゆの)牧(まき)
楞厳寺(りょうごんじ)地図<外部リンク>
[毎月17日に7時から17時まで一般公開]
時代:藤原時代
この像は像高4、29センチと両手に収まるほど小さく作りも素朴ですが、頭部が大きく膝張りが小さい、膝高が低く衣の先の流れが見られないなどの作風から、藤原時代のものと考えられます。材質は金で、宝冠を被り、右手は膝頭に置き左手は臂(ひじ)を曲げ、結跏趺座(けっかふざ)という坐り方をした、菩薩形の仏様です。
嘉永6(1853)年、好松(よしまつ)という村人が楞厳寺裏手、日尾山(ひごやま)の頂上付近で土中から発見し寺に奉納したといわれています。
この経緯を当時の住職貫之(かんし)和尚が「日尾山土中出現黄金像正観世音縁起(ひごやまどちゅうしゅつげんおうごんぞうしょうかんぜおんえんぎ)」に書き記し、発見場所に石碑も建立しています。
全国で発見された黄金仏は、昭和58年に山伏の修験場として知られる奈良県の大峰山寺(おおみねさんじ)から出土した、阿弥陀如来坐像(像高3、12センチ)と菩薩形坐像(像高2、85センチ)の2躯のみです。