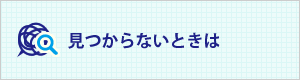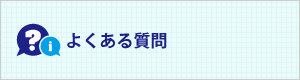長穂念仏踊

県指定無形民俗文化財
指定年月日:昭和43年4月5日
所在地:周南市長穂(ながお)門前(もんぜん)
龍文寺(りゅうもんじ)地図<外部リンク>
龍文寺は、陶(すえ)氏菩提寺として永亨元(1429)年、陶盛政(すえもりまさ)により創建されました。寺に伝わる念仏踊の由来は、次のように伝えられています。
『大内義隆(おおうちよしたか)を討った陶隆房(すえたかふさ=後の晴賢)は、弘治元(1555)年、厳島(いつくしま)の戦で毛利元就(もうりもとなり)に敗れ自刃、若山(わかやま)城にいた晴賢(はるかた)の子・長房(ながふさ)と小次郎は、杉重輔(すぎしげすけ)の軍に攻められ龍文寺へ立て籠もった。錦川(にしきがわ)と険しい山々に囲まれた寺は堅固な要塞でもある。寄せ手は一計を案じ、古くから伝わる周方神社祭礼の踊りに紛れて寺内に乱入、激しい戦いの末、寺に籠もった人々はことごとく討ち果たされた。その後、陶氏追善供養のため毎年7月7日にその踊りを伝え、やがて雨乞い踊りへと変化し現在まで続いているという。』
龍文寺陥落後、陶方の城は次々に落城、弘治3(1557)年3月、晴賢の孫(一説には末子)鶴寿丸(かくじゅまる)も、長府(ちょうふ)の長福寺(ちょうふくじ)(現、下関市功山寺)で最期を遂げ、陶氏は滅亡しました。
敬語(よみたて)という祝詞(のりと)を唱え、笛、鐘、太鼓に合わせて籠や鶏の冠をつけて古式ゆかしく踊ります。以前は木津(こつ)、門前地区の跡継ぎの男子だけに伝えられていましたが、やがて長穂全体の青年によって踊られるようになり、昭和60年からは長穂中学校(現、翔北中学校)の生徒により伝承されています。