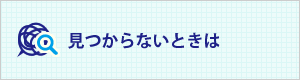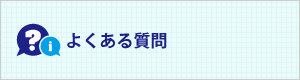式内踊(しきないおどり)

県指定無形民俗文化財
指定年月日:昭和43年4月5日
所在地:周南市大向(おおむかい)二俣(ふたまた)
二俣神社
地図<外部リンク>
二俣神社は延長5(927)年に完成した法典『延喜式(えんぎしき)』に記載されています「延喜式内社(えんぎしきないしゃ)」で、由緒のある神社です。
およそ350年昔、大向、長穂(ながお)、鹿野(かの)村の氏子が集まって春秋の例祭や夏の青田御祈祷(あおたごきとう)の祭りを行っていました。ある年の青田御祈祷の際、村々が御神体を持ち帰ろうと争っていると突然重くなり、抱えきれずに錦川に投げ入れてしまいました。驚いた神主は、川に飛び込み元通りに安置しましたが、その年から日照りや洪水が絶えず、稲穂は枯れ、大飢饉となったのです。村々は反省し、二俣地区の若者を代表として伊勢神宮へ参拝させ、その道中に習い覚え、伝えたのが式内踊りであるといわれています。
沐浴し身を清めた若者が、五穀豊穣、疫病退散、神の加護を願って神社に踊りを奉納しました。道行きから筑羽根(つくはね)まで24種類の踊りがあり、魔除役の剽軽(ひょうきん)と呼ばれる鬼2人と天狗1人を中心に、五色のたすきをまとい、杖を手に、迫力ある踊りを繰り広げます。
5年または7年ごとの八朔(はっさく)祭に踊り継がれ、昭和30年には式内踊保存会を結成、現在は翔北中学校の生徒により伝承されています。