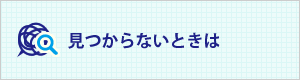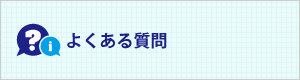絹本著色陶弘護像(けんぽんちゃくしょくすえひろもりぞう)

国指定重要文化財(絵画)
指定年月日:昭和49年6月8日
所在地:周南市大道理(おおどうり)門前(もんぜん)
龍豊寺(りゅうほうじ)地図<外部リンク>
※周南市美術博物館寄託
[美術博物館にてレプリカを常時展示中]
時代: 室町時代文明16(1484)年
陶(すえ)氏は、南北朝から室町時代にかけ、大内氏の重臣として活躍し、徳山・新南陽地域を領していました。
弘護は康正元(1455)年9月3日に生まれ、応仁元(1467)年応仁の乱で父弘房(ひろふさ)が戦死したため13歳で陶氏の当主となりました。その後、大内氏の内乱を治めるなど活躍しましたが、文明14(1482)年5月27日、長年敵対関係にあった津和野・三本松城の吉見信頼(よしみのぶより)と大内氏の館で争い、28歳で世を去りました。院号は昌龍院殿建忠孝勲(しょうりゅういんでんけんちゅうこうくん)で、供養塔は陶氏の菩提寺、長穂(ながお)の龍文寺(りゅうもんじ)にあるとされていますが、実物は発見されていません。
龍豊寺は文亀元(1501)年、夫の菩提を弔うため弘護の室・龍豊寺殿咲山妙听大姉(りゅうほうじでんしょうざんみょうきんだいし)が創建したもので彼女の供養塔が寺の東南、開基杉のたもとに建っています。また、弘護には武護(たけもり)、興明(おきあき)、興房(おきふさ)の三男一女があり、後に厳島(いつくしま)で毛利元就(もうりもとなり)と戦った晴賢(はるかた)は孫にあたります。
この絵は三回忌にあたる文明16(1484)年に描かれ、雪舟(せっしゅう)の筆といわれます。安定した構図、伸びやかな描線は見事で、英邁(えいまい)といわれた弘護の面影をよく伝えています。賛は雪舟とも親交のあった禅僧以参周省(いさんしゅうしょう)によるもので、陶氏だけでなく大内氏の歴史を知る上での貴重な史料として、非常に高い意義を持っています。