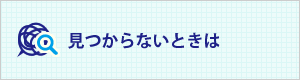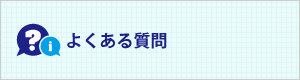罹災証明書の申請と発行について
印刷用ページを表示する更新日:2025年10月16日更新
風水害や地震等の自然災害によって、お住いの住家等が被害を受けた場合、被害にあわれた方を対象に罹災証明書を発行します。
罹災証明書とは
- 罹災証明書とは、風水害や地震等の自然災害により被災した住家の被害について市の職員が被害認定調査を行い、確認した罹災程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部半壊))について、市長が交付する証明書です。
- 罹災証明書は、災害見舞金等の受給申請や、介護保険料、保育料等の減免申請などに必要となります。
※火災による罹災証明書については、火災で被害を受けた場所を所管する消防署にて発行します。
対象者
- 災害発生時に市内に居住し、住家(持家か賃貸かは問わず)に被害が発生した世帯
- 災害発生時に市内において住家を所有している方
住家とは
- 住家とは、現実に居住のため使用している建築物のことを言います。
- 非住家とは、住家以外の建築物、例えば、倉庫、カーポートなどのことを言います。
※罹災証明書は原則、非住家に対しては交付されません。非住家に対しては「被災証明願」により被災したことの証明書を発行します。
被災証明の申請と発行についてはこちらをクリックしてください。
申請方法
以下のものをご記入のうえ、必要な書類等を添えて課税課、または、各総合支所の窓口へご提出ください。
※災害が発生してから期間が経過した場合や修理をした後では、被害の判定ができないため罹災証明書を発行できない場合があります。災害発生後できる限り早めの申請をお願いします。また、災害と被害の因果関係が確認できる写真を撮影しておいてください。
写真撮影のポイント [PDFファイル/776KB]
申請に必要な書類等
- 罹災証明書交付申請書 [PDFファイル/190KB]
- 罹災証明書交付申請書 [Excelファイル/26KB]
- 罹災証明書交付申請書(記入例) [PDFファイル/285KB]
- 申請者本人が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)を窓口で提示
- 被害の状況が分かる写真等
発行までの流れ
- 申請後、市の職員が被災現場を訪問し、被害認定調査を行います。
- 被害認定調査には、居住されている方、または、所有されている方の立会が必要となりますので、ご協力をお願いします。
- 調査終了後に、課税課よりご連絡させていただき、罹災証明書を発行します。
- 原則、本庁課税課または各総合支所担当課窓口にて交付いたします。
- 郵送がご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、課税課(家屋・償却担当)までご送付ください。
- 罹災証明の証明手数料は必要ありません。
国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」で罹災証明書の申請ができます。
ぴったりサービス<外部リンク>