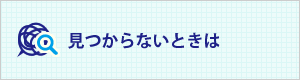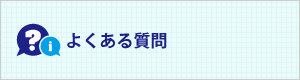令和7年度ハートフル人権セミナーの報告について
令和7年度ハートフル人権セミナーの報告について
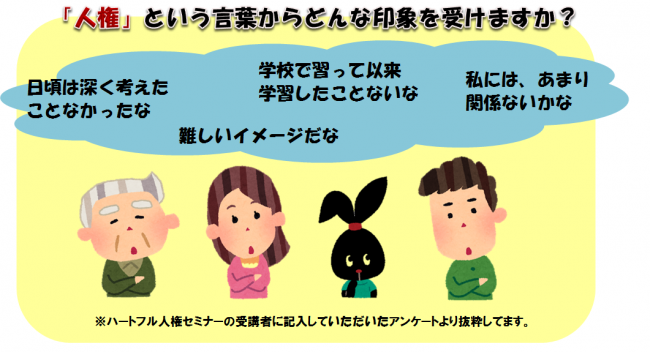
「人権」ってなんだろう?
周南市教育委員会では、身のまわりにある人権課題について学ぶ機会がもてる
よう、毎年、各施設で人権研修(ハートフル人権セミナー)を開催しています。
人権課題は時代の流れや社会背景によって常に変化しています。
皆さんも、ハートフル人権セミナーを受講してみませんか?
きっと、自分の持っている情報のアップデートにもつながり、「人権」について
正しい理解と認識をさらに深めることができると思います。
ご参加をお待ちしております!
ハートフル人権セミナーの内容
さまざまな人権課題の講座
さまざまな人権課題について講話や体験学習などを通して考えます。
ハートフル人権セミナーの講座では、会場ごとに内容が異なり、子どもの問題、外国人問題、男女共同参画に関する問題、インターネットにおける問題、高齢者問題、ハンセン病問題、性の多様性、部落差別(同和問題)、障害者問題などの人権課題について学びます。
これまで実施したセミナー
| 開催日(曜日) | 会場 | 人権課題の テーマ |
内容及び講師 |
| 6月4日(水曜日) |
大河内市民センター (勝間・大河内地区) |
障害者問題 |
講話「聴こえづらいを考える~当事者からの声・疑似体験を通して~」 講師:山口県中途失聴者・難病者協会 重村 智子 氏、周南市社会福祉協議会職員 (感想) 当事者からの話で、どのように接してほしいのか、話しかけてほしいのかを聴くことができて、とてもよかった。初めてイヤーマフ体験をしましたが、聞こえない、聞こえづらいことで、どういう不便があるかよく分かりました。 |
| 6月5日(木曜日) |
久米市民センター (久米地区) |
外国人問題 |
講話「外国人と共に暮らすために私達ができる事」 講師:ICCO文化交流創成コーディネーター(AFS日本協会) 古川 惠子 氏、豊嶋 由美子 氏 (感想) 外国人に対しての思い込みや自分の価値観だけで接することがあったと気づかされました。私のもつ文化も、海外からみたら、きっと異文化なんだと感じました。自分の価値観で物事を決めつけず、相手のことを気遣い、コミュニケーションをとっていきたいと思いました。楽しい時間をありがとうございました。
|
| 6月10日(火曜日) |
戸田市民センター (西部地区) |
ハンセン病問題 |
講話「ハンセン病問題から学ぶ~偏見や差別を受けてきた人々の思いにふれて~」 講師:人権教育課 職員 (感想) 無知の“こわさ”を思い知らされました。差別や偏見をいつの間にか自分もしていないか、言動や行動を振り返る良い機会になりました。ハンセン病の歴史を知ることができてよかったです。 |
| 6月 12日(木曜日) |
新南陽ふれあいセンター (福川地区) |
インターネットにおける問題 |
講話「ネット社会でのトラブルで、加害者にも被害者にもならないために」 講師:金融経済教育推進機構(JーFLEC)認定アドバイザー 岡本 浩司 氏 (感想) スマホやネットの進化に伴い、犯罪が複雑多様化していることを改めて感じました。それと同時に自分自身の人権感覚も常にアップデートしていないと、知らないうちに加害者になり得ることもよく分かりました。 |
| 6月19日(木曜日) |
菊川市民センター (菊川地区) |
部落差別(同和問題) |
講話「小・中学校教科書で学ぶ同和問題」 講師:元社会教育指導員 三奈木 正紀 氏 (感想) とても分かりやすく良かったです。多数派が正しいとかではなく、一人ひとりにある気持ちは違っていて、認め合いながら思いやりの気持ちを忘れず人と関わっていきたいと思いました。 |
| 6月 24日(火曜日) |
須々万市民センター別館 (北部地区) |
子どもの問題 |
講話「地域で子どもを守り育てるために、子供の権利について考える~里親養育サポートの視点から~」 講師:里親養育サポートセンター(れりーふ)長 小林 有 氏 (感想) 里親制度について、くわしく知ることができました。何かお手伝いできることがあればと考えるきっかけ作りとなりました。今回の講座で学んだ子どもとの関わり方を実践したいと思います。 |
| 6月 26日(木曜日) |
コアプラザかの (鹿野地区) |
性の多様性に関する問題 |
講話「多様な性から多様性を考える」 講師:山口県立下関南総合支援学校 教諭 今田 真樹 氏 (感想) 性のセミナーを受けたのは初めてだったのですが、LGBTについて真剣に考えるとてもよいきっかけになりました。自分の周りにも当事者の方はいるかもしれない。その人たちのためにも、自分の行動や考えを見直し、安心して暮らせる社会をつくっていくことが大切だと思いました。 |
| 7月3日(木曜日) |
今宿市民センター (今宿地区) |
犯罪被害者と 家族の問題 |
講話「当たり前の日々は奇跡の連続」 講師:交通死亡事故被害者遺族 池田 かおり 氏 (感想) 子どもを失う辛さは想像すらできないことです。会えてよかった、そう思い、前を向いておられる池田さんのお話に涙が出ました。当たり前ではないこの日常に感謝することを忘れず、これからの人生を生きていきたいと思います。 |
| 7月29日(火曜日) |
櫛浜市民センター |
部落差別(同和問題) |
講話「小・中学校教科書で学ぶ同和問題」 講師:元社会教育指導員 三奈木 正紀 氏 (感想) 同和問題について正しく理解し、向き合っていくことが大切だと思いました。教科書の記述などからこの問題の流れがよく理解できました。ビデオなどもあり、分かりやすかったです。子どもたちとも人権感覚についてしっかり考えていきたいと思います。 |
| 9月9日(火曜日) |
三丘市民センター (高水・三丘・八代地区) |
高齢者 |
講話「認知症を学び、みんなで考える~認知症サポーター養成講座~」 講師:地域福祉課(熊毛総合支所市民福祉課)保健師 (感想) 実際に認知症の疑いがある方をサポートしておられるご家族のお話がとても感慨深かったです。認知症は他人事ではなく、身近な問題で、自分事でもあると再認識できました。適切な対応への心得を忘れないようにしたいです。 |
| 9月11日(木曜日) |
秋月市民センター (秋月地区) |
こころの健康 |
講話「見逃さないで ~一人ひとりが誰かのゲートキーパーに~」 講師:健康づくり推進課職員・周南公立大学人間健康科学部 講師 福森 絢子 氏 (感想) 相手の話に耳を傾け、自分の意見を押し付けず、相手の気持ちを受け入れるといった「話を聴くときのポイント」を学ぶことができました。また、対応の良し悪しを具体的に知っておくことが大事だと思いました。できることから実践していきたいと思います。 |
| 9月18日(木曜日) |
遠石市民センター (遠石・周陽・桜木地区) |
インターネットにおける問題 |
講話「情報化社会に自分らしく生きるために~人権の視点から~」 講師:周南公立大学総合教育部 講師 中嶋 克成 氏 (感想) 生活をする上で、ふれることの多い情報をどう扱っていくかをしっかり考えていかないといけない時代になったのだと感じました。買い物レシートやSNSなどから、簡単に個人情報が抜き取られることに驚きました。情報社会に生きている自覚をもち、改めて情報モラルについて考えたいと思いました。 |
| 9月26日(金曜日) |
櫛浜市民センター (櫛浜地区) |
外国人問題 |
講話「共に生きる社会をめざして~留学生と『多文化共生』を考える~」 講師:周南公立大学 留学生(5名)、国際交流担当職員
(感想) 5つのグループに分かれ、留学生の人たちと国による文化習慣の違いなどについて紹介し合い、興味深い話で盛り上がりました。国によって学校の始まる月が違ったり、義務教育の年数が違ったり、いろいろな違いを学ぶことができました。人によって、国によって、普通が違うということを踏まえて、多文化交流を深めたいと思いました。 |
| 9月30日(火曜日) |
岐山市民センター (岐山地区) |
障害者問題 |
講話「音楽が培う一人ひとりの人権意識~音楽療法士の視点から~」 講師:音楽療法士 植木 浩子 氏 (感想) 音楽を通して人とつながるきっかけになったり、自己表現をできるようになったり、もっている力を引き出すことができるってすばらしいと思いました。障害のある子どもたちが音や音楽を楽しみながら、仲間とつながって、一つの作品を作り上げていく姿に心打たれました。 |
| 10月2日(木曜日) |
学び・交流プラザ (富田・和田地区) |
男女共同参画に関する問題 |
講話「家庭・地域での男女共同参画をみんなで考えよう」 講師:男女共同参画推進員 (感想) 寸劇がすごくよかったです。自分の気持ちを伝えること、相手の話を柔らかく聴けることができる人でありたいと思いました。家族や周りの人への感謝を忘れないようにしたいと思います。グループワークもよく話し合えてよい時間になりました。 |
| 10月7日(火曜日) |
周南市役所 多目的室 (中央・関門地区) |
子どもの問題 |
講話「子どもまんなか社会に向けた子どもの権利について~児童相談所からの視点で~」 講師:山口県周南児童相談所長 (感想) わが子との関わり方だけではなく、社会での自分の在り方や他の子どもたちへの目の配り方なども考えさせられるよい機会をいただいたと思います。親として、子どもを支える地域住民として、子ども一人ひとりの安心して生きる権利が損なわれないよう守り育てていく責任を、自作されたイラストとスライドを観て改めて感じました。 |