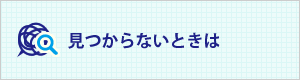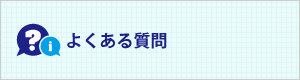離婚届
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
婚姻関係を解消させたいときは、この届出をしてください。
離婚届の種類
当てはまる記事をご覧ください。
離婚届(協議離婚)
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
- 離婚届書※成年者の証人が2人必要
- 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※詳しくは本人確認書類の種別 [PDFファイル/560KB]をご確認ください。
離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、別の届出が必要です。
→離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2項の届)
離婚届の書き方
離婚届の書き方 [PDFファイル/466KB] 届出について [PDFファイル/134KB]
離婚に伴う主な手続き
- マイナンバーカード
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 国民健康保険(加入者のみ)
氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。 - 印鑑登録(登録者のみ)
氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。 - 住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます。
(詳しくは、こちらのページをご覧ください)
※市民課以外で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。
- 高齢者支援課(介護保険証について)※氏が変わった方のみ
- 障害者支援課(障害者手帳、福祉医療費受給者証について)※氏が変わった方のみ
- 子育て給付課(児童手当、児童扶養手当について)
- 離婚時の年金分割
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後二年以内に手続を行っていただく必要があるのでお早めにお近くの年金事務所までご相談ください。(詳しくは、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください) - 離婚の際の養育費と面会交流について(詳しくは、こちらのページをご覧ください)
- 離婚の際の子の養育に係るルールが変わります(詳しくは、こちらのページをご覧ください)
離婚届(裁判離婚)
届出期間
調停・和解の成立、請求の認諾または裁判確定の日から10日以内
※成立日・認諾日・確定日を1日目とします。
届出人
調停・裁判・和解の申立人、認諾の請求をした人または裁判の訴えを提起した人
※上記届出人が届出期間内に届出しないときは、相手方も届出できます。
届出に必要なもの
- 離婚届書※証人は不要
- 調書の謄本または審判・判決書の謄本と確定証明書
- 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、別の届出が必要です。
→離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2項の届)
離婚に伴う主な手続き
- マイナンバーカード
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 国民健康保険(加入者のみ)
氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。 - 印鑑登録(登録者のみ)
氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。 - 住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます。
(詳しくは、こちらのページをご覧ください)
※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。
- 高齢者支援課(介護保険証について)※氏が変わった方のみ
- 障害者支援課(障害者手帳、福祉医療費受給者証について)※氏が変わった方のみ
- 子育て給付課(児童手当、児童扶養手当について)
- 離婚時の年金分割
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後二年以内に手続を行っていただく必要があるのでお早めにお近くの年金事務所までご相談ください。(詳しくは、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください) - 離婚の際の養育費と面会交流について(詳しくは、こちらのページをご覧ください)
- 離婚の際の子の養育に係るルールが変わります(詳しくは、こちらのページをご覧ください)