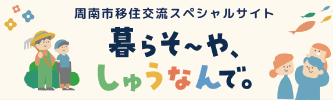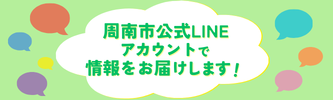本文
国民健康保険の給付
国民健康保険の給付を受けるには申請が必要です。
| 種類 | こんなとき | 内容 | 申請に必要な書類など | |
|---|---|---|---|---|
|
療養費 |
やむを得ない理由でマイナ保険証、資格確認書等なしで医療を受けたとき |
保険給付分の払い戻しが受けられます。 |
・受診した医療機関の領収証 |
いずれの場合も |
|
・コルセットなどの補装具を作ったとき |
・保険医の診断書または証明書 ※上記に加え、靴型装具を作成した場合には、装具を装着した全身写真の添付が必要となります。 |
|||
|
海外療養費 |
海外渡航中に病気やケガなどで治療を受けたとき |
・海外の医療機関の診療内容明細書とその和訳(訳した方の署名が必要) |
||
|
出産育児一時金 |
国保の被保険者に子どもが生まれたとき |
産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合は、50万円が支給されます。それ以外の場合は48.8万円が支給されます。
【直接支払制度とは】
|
○医療機関等で直接支払制度を利用された場合 (医療機関等で出産育児一時金の申請および受け取りについての代理契約を交わされた場合)
・出産費用が50万円を超えた場合 医療機関等へ差額をお支払ください。
・出産費用が50万円を下回った場合 次の書類をご用意していただき、市へ差額をご請求ください。 ・医療機関等と交わした代理契約合意文書 ・医療機関等の請求明細書 ・世帯主名義の口座番号の分かるもの ・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(※1) ・母子健康手帳
|
|
|
〇医療機関等で直接支払制度を利用されない場合 ・直接支払制度を利用しない旨を確認できる書類 ・医療機関等の領収明細書 ・世帯主名義の口座番号の分かるもの ・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(※1) ・母子健康手帳 |
||||
|
〇海外で出産された場合 ・在留カードまたは特別永住者証明書(出産した方が外国人の場合) ・出産証明書とその和訳(訳した方の署名が必要) ・出産した方のパスポート(出産時の渡航歴が分かるもの) ・世帯主名義の口座番号の分かるもの ・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(※1) ・母子健康手帳 ・現地の公的機関が発行する戸籍や住民票(出生したお子様の住民登録が海外にある場合) ・調査に関わる同意書(窓口に様式があります) 海外出産に係る不正請求を未然に防止する観点から、支給申請に対する審査を強化しております。不正請求の疑いがある場合には、警察と連携して厳正な対応を行います。 |
||||
|
〔注意事項〕
|
||||
|
葬祭費 |
国保の被保険者が死亡したとき |
5万円が支給されます。 |
・亡くなった方の資格確認書 ・世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(※1) ・死亡診断書(死亡の原因が病死(老衰含む)以外の場合や、修学中や施設等入居での住所地の特例の適用を受けている場合)
[注意事項] 1.別の健康保険や制度から葬祭費にあたる給付が受けられる場合は、周南市国民健康保険からの葬祭費の支給はありません。(社会保険の被保険者であった方が退職後3ヶ月以内に亡くなり、社会保険から埋葬費が支給される場合等) 2.葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効となり、申請できなくなります。 |
|
|
高額療養費 |
医療費の支払が高額になったとき |
一か月の自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。
|
・世帯主名義の口座番号の分かるもの ・支払った医療費の領収証の添付を求める場合があります。 ・世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(※1) |
|
(※1)世帯主と対象者のマイナンバーが必要になります。マイナンバーについての詳細はこちら
こんなときは手続きが必要です。
| こんなとき | 対象者 | 内容 | 交付されるもの | 手続きに必要な書類など |
|---|---|---|---|---|
|
人間ドックを受けたいとき |
一般・・・30歳以上 |
費用の7割を国保が負担します。 3割を受診機関でお支払いください。 |
詳しくはこちらのページをご覧ください |
|
|
外来や入院時の自己負担額が高額になるとき |
|
マイナ保険証をお持ちの方は、認定証の申請は不要です。(※2) 窓口での自己負担額が自己負担限度額まで減額されます。 |
限度額適用認定証 |
・対象者の資格確認書または本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(※1) |
|
入院時の食事代の減額を受けたいとき |
住民税非課税世帯のうち、70歳未満の人 |
マイナ保険証をお持ちの方は、認定証の申請は不要です。(※2) ただし、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、申請が必要です。(※3) 入院したときの一食あたりの食事代が減額されます。 |
標準負担額減額認定証 |
・対象者の資格確認書または本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(※1) |
|
入院時の自己負担限度額及び食事代の減額を受けたいとき |
住民税非課税世帯の人 |
マイナ保険証をお持ちの方は、認定証の申請は不要です。(※2) ただし、所得区分オまたは低所得2の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、申請が必要です。(※3) 窓口での自己負担額が自己負担限度額となり、一食あたりの食事代が減額されます。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
・対象者の資格確認書または本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・(90日を超えた入院の場合)領収証など ・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(※1) |
|
長期高額疾病患者の自己負担額の減額を受けたいとき |
・人工透析を必要とする慢性腎不全 |
一か月あたりの自己負担限度額が入院・外来各1万円になります。(ただし平成18年10月1日から70歳未満の上位所得者については人工透析を必要とする慢性腎不全の場合2万円になります) |
特定疾病療養受療証 |
・対象者の資格確認書または本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・保険医の証明書など |
|
はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受けたいとき |
国保の被保険者 |
一術800円、併術1,000円が割り引かれます。(1ヶ月12回まで) |
特になし |
施術所 [PDFファイル/98KB]に被保険者番号等を確認できるもの [PDFファイル/348KB]と印鑑をお持ちのうえ施術を受けてください。 |
|
高額療養費の貸付を受けたいとき |
国保の被保険者 |
高額療養費相当部分を社会福祉協議会が立て替えて支払います。 |
|
|
|
交通事故など第三者の行為によるケガなどの治療を国保で受けたいとき |
国保の被保険者 |
医療費をいったん国保が立て替え、後で過失割合に応じて第三者に請求することになります。 |
|
詳しくは、こちらのページをご覧ください。 |
(※1)世帯主と対象者のマイナンバーが必要になります。マイナンバーについての詳細はこちら
(※2)マイナ保険証をお持ちの人は、マイナ保険証の利用により医療機関等で限度額適用区分等を確認できるため、認定証が交付されません。マイナ保険証についての詳細はこちら
(※3)住民税非課税世帯(所得区分オ、低所得2)で過去1年間の入院日数が90日超になった方のうち、食事代の減額対象である場合は、マイナ保険証の有無に関わらず、限度額適用認定証の申請が必要です。「入院したときの食事代について」をご確認ください。
【マイナ保険証をご利用いただく場合の注意事項】
・保険料に滞納がある場合は情報が反映されません。また、所得を確認できない場合は、正しい区分となりません。
・医療機関によっては、マイナ保険証を利用できない場合があります。マイナ保険証の利用については受診される医療機関へ直接お問い合わせください。
高額療養費の自己負担限度額
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当※1 |
|---|---|---|
| 所得(※2)が901万円超 | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| 所得が901万円以下600万円超 | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
| 所得が600万円以下210万円超 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 所得が210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
| 所得区分 | 自己負担限度額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人単位)【1】 | 外来+入院(世帯単位)【2】 | |||
| 多数該当 | ||||
| 住民税課税所得 690万円以上 |
現役並み所得者3(※3) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
| 住民税課税所得 690万円未満 380万円以上 |
現役並み所得者2(※3) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
| 住民税課税所得 380万円未満 145万円以上 |
現役並み所得者1(※3) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
| 一般世帯(※4) | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税 非課税世帯 |
2(※5) | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
| 1(※6) | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
(※1)多数該当とは、過去1年間に3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降にあたります。
(※2)所得=総所得-基礎控除(43万円)
(※3)現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上の人にあたります。
(※4)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(※5)2とは、世帯員全員が住民税非課税の人にあたります。
(※6)1とは、2のうち所得が0円の人にあたります。(ただし年金収入は年間80.67万円以下となります。)
≪高額療養費の計算方法≫
70歳未満の人の場合
-
月の1日から末日までの受診を一か月として一か月単位で計算します。
-
同じ月内であっても、違う医療機関を受診した場合は別計算となります。
-
同じ医療機関でも入院と外来、医科(内科・外科など)と歯科は別計算となります。
-
外来での自己負担額と、その受診の院外処方せんに基づく薬剤の自己負担額は合算できます。
-
上記の1から4までの条件に基づく計算で、支払った自己負担額が21,000円(合算対象基準額)以上のものを対象とし、それらの金額を合算します。
※保険診療が適用されないもの(差額ベッド代など)や入院時の食事代は対象になりません。
70歳以上の人の場合(後期高齢者医療を受ける人は除く)
-
同じ月内に支払った自己負担額はすべて合算できます。
-
まず個人単位で外来の自己負担限度額(表B【1】)を適用し、その後で入院分を合算し、自己負担限度額(表B【2】)を適用します。
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合
-
まず70歳以上の人の高額療養費を計算します。
-
その後で、合算対象基準額以上の自己負担額を合算し、表Aの自己負担限度額を適用します。
入院したときの食事代について
住民税非課税世帯のうち、マイナ保険証をお持ちでない人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。国保担当窓口に申請してください。
ただし、住民税非課税世帯の人のうち、70歳未満の人と70歳以上の低所得者2に該当する人は、過去1年間の入院日数が90日を超えた時点で再度申請が必要です。
長期入院該当者として認定されれば、入院時の1食あたりの食事代が190円になります。申請日を基準に認定を行いますので、お早めに手続きをしてください。※療養病床の場合は1食あたり240円。
マイナ保険証を利用されている方も、長期入院該当者として認定を受けるためには、必ず申請が必要です。マイナ保険証についての詳細はこちら
長期入院該当の認定は、毎年7月末、70歳以上・75歳以上の保険証に切り替わる日の前日で切れるため、該当の人は再度申請してください。
| 所得区分 | 標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| (1食あたり) | |||
| 住民税課税世帯の人 | 510円(※1) | ||
| 住民税非課税世帯 | 70歳未満の人と 70歳以上で 低所得者2の人 |
90日までの入院 | 240円 |
| 91日以上の入院 (過去1年の入院日数) |
190円(※2) | ||
| 70歳以上で低所得者1の人 | 110円 | ||
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。
| 所得区分 |
食費 |
居住費 | |
|---|---|---|---|
| (1食あたり) | (1日あたり) | ||
| 住民税課税世帯の人 | 510円(※3) | 370円 | |
| 住民税非課税世帯 | 70歳未満の人と 70歳以上で 低所得者2の人 |
240円 | |
| 70歳以上で低所得者1の人 | 140円 | ||
| 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
|---|---|---|
| 上記の「入院時食事療養費の 標準負担額」と同額の 食材料費相当額を負担 |
370円(難病患者は0円) | |
※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は300円。
※2 過去1年間の入院日数が合計で90日を超えた場合です。再度申請が必要です。
※3 一部医療機関では470円。
国民健康保険一部負担金の減免等ついて
災害や失業、廃業等で生活が困難となった場合には、医療機関で支払う一部負担金について減免される場合がありますので、詳しくは保険年金課へお尋ねください。
高額介護合算療養費について
同一世帯(同一医療保険)で、高額療養費の算定対象世帯において介護保険受給者がいる場合には、医療と介護の自己負担額を合算して、下記の限度額を超える自己負担額については、申請によりそれぞれの制度から払い戻されます。
| 所得(基礎控除後の総所得金額等) | 限度額 |
|---|---|
|
901万円超 |
212万円 |
|
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
|
210万円超~600万円以下 |
67万円 |
|
210万円以下 |
60万円 |
|
市民税非課税世帯 |
34万円 |
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3(住民税課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得者2(住民税課税所得380万円以上) | 141万円 |
| 現役並み所得者1(住民税課税所得145万円以上) | 67万円 |
|
一般世帯 |
56万円 |
|
非課税世帯(低所得者2) |
31万円 |
|
非課税世帯(低所得者1) |
19万円 |
算定期間
・毎年8月~翌年7月までの1年間
その他
・自己負担額からは、高額療養費および高額介護サービス費相当額を除きます。
・支給額が500円を超えないときは、支給対象となりません。
・医療と介護の自己負担額のいずれかが0円の場合は、支給対象となりません。